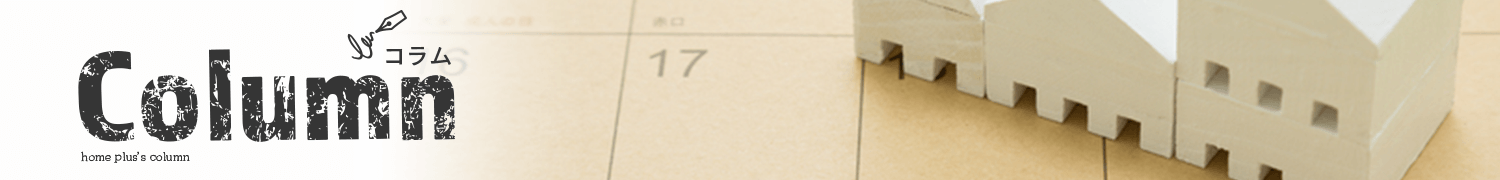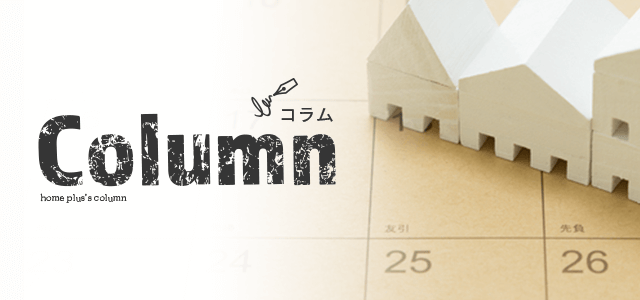コラム

団地リノベーションで注目されているのが「壁で仕切らない」空間づくり。
可動式家具やパーテーションを活用し、暮らしに合わせて柔軟に使える住まいが今、選ばれています。
今回は、そんな“ゆるやかに区切る”新しい空間の使い方と、その魅力についてご紹介します。
1.壁で仕切らない、自由な空間づくりの団地リノベ
最近の団地リノベーションの傾向として、従来の「壁で仕切る」間取りから、完全な壁をつくらず、視線や光を通すことで、お部屋の自由度を上げ、開放感を得られる“空間をゆるやかにつなげるスタイル”を希望する方が増えています。
たとえばですが、リビングとダイニングの間に低めの収納家具やシェルフを配置することで、圧迫感なくゾーニングする事が可能となり、レイアウトの変更も簡単に行えます。
このように、一度建てたら動かせない「壁」を設けず、空間の役割をふんわりと分けつつも、家族の気配を感じながら過ごせる心地よさはとても魅力的です。限られた広さを有効活用し、住まいに広がりと自由をもたらす「仕切らない工夫」は、今の暮らしにフィットした新しいリノベーションの形ですね。
2.可動式家具やパーテーションで叶える柔軟な暮らし
空間を自由に使い分けるために活躍するのが、家具やパーテーションといった“動かせる仕切り”です。
固定された壁とは違い、暮らしの変化に合わせて配置を変えられる点が大きなメリット。
たとえば在宅ワークや子供が勉強でデスクを使う場合はパネルで集中できる作業・勉強スペースを設け、終わったらパネルを片づけて家族が過ごすリビングを広く取るなど。
天井から下げるロールスクリーンを使えば、光や風を通しながら適度なプライバシーも確保できますし、子どもの成長に合わせて間取りを変えることも工事なしで実現できます。
団地のように限られた空間でも、工夫しだいで驚くほど柔軟な暮らしが可能になるのです。
空間の仕切りとして家具を利用するのも一つの方法です。選び方を工夫して、空間の印象・暮らし方を大きく変えていきましょう。
3.変化に対応できる“余白”を楽しむ団地リノベーション
住まいに少しの“余白”を残すことで、暮らしはぐっと柔軟になります。
リノベーションの際は、最初から用途を決めすぎず、多目的に使えるスペースを意識的に設けることがポイントです。 たとえば、何も置かない一角が、子どもの遊び場として、または、来客用の寝室にと、さまざまな目的で使用することができます。将来にわたって長く暮らしていく自宅とはいえ、ライフステージの変化や趣味、働き方など、暮らしは常に変わっていくもの。
その変化に対応できる“余白”のある空間づくりが、長く快適に住むためのポイントでもあります。
団地というコンパクトな住まいだからこそ、詰め込みすぎず、あえて余白を残す設計を意識しながら、使いやすさと住み心地の良さを追求しましょう。
まとめ
今回は、団地という、限られた広さにおける空間の使い方についてご紹介しました。
住まいのレイアウトは壁だけで造るものではありません。仕切り方や“余白”の工夫しだいで、暮らしはもっと自由に、もっと快適に変えられますので、ぜひ、ご自分らしい空間の使い方を楽しみながらイメージしてみてくださいね。