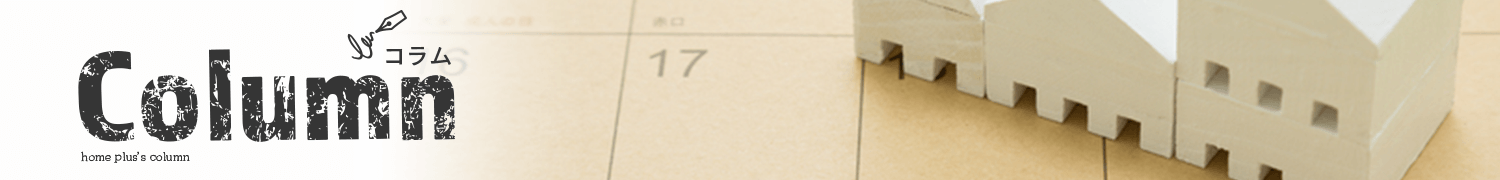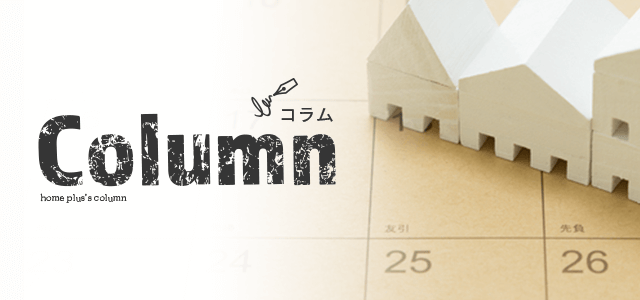コラム

団地でのリフォームでは、「共用部分」と「専有部分」という明確な線引きがあります。
リフォームを行うにあたっては管理組合の承認が必要なケースも多く、規約や制限を知らずに進めるとトラブルになることも。
今回のコラムでは団地リフォームで“できること・できないこと”をご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
団地リフォームの基本ルール「専有部分」と「共用部分」
団地や公団住宅などでは、住まい全体が個人の所有ではなく、建物を住人全体で共有しています。
そのため、リフォームができるかどうかは個人の所有である「専有部」と住人全体の所有である「共用部」に分けられ、自らの判断で手を入れられるかどうかが異なります。
「専有部」は、世帯ごとの部屋の中の壁や床、天井の内側などで、この部分は自分で自由に改修(リフォーム)できる場所です。
一方の「共用部」は、躯体としての柱や梁、外壁、玄関ドア、窓サッシなど、建物全体の構造に関わる部分を指します。
リフォームを考えるときは、まず自分の家のどこまでが専有部分で、どこからが共用部分なのかをしっかり確認しておきましょう。
実際にできるリフォーム例・制限されるリフォーム例
団地では、リフォームの内容によって「自由にできる」ものと「制限がある」ものがあります。
■“できる” リフォームの例
・床の張り替え(畳からフローリングなどへ)
・壁紙の貼り替え
・キッチン、浴室、トイレなどの設備交換
・室内ドアや収納の変更や造作
・照明やスイッチの位置変更や追加
これらは「専有部」にあたるため、基本的には自由に行うことができます。
ただし、床材を変更する場合は「遮音等級(L値)」の指定がある団地もあるため注意しましょう。
■“制限される” または “申請が必要” なリフォームの例
・玄関ドアの交換(特に外側部分)
・窓サッシや網戸の交換
・ベランダの床や手すりの変更
・配管や配線の経路変更
・外壁や共用廊下に面する部分の工事
これらは建物の「共用部」にあたるため、入居者が勝手に改修することはできません。
設備の劣化が著しいなど、どうしても改修が必要な場合はまず管理組合へ相談し、必要な申請・承認を得てから進めるようにしましょう。
団地リフォームをスムーズに進めるための注意点と手続き
■団地でリフォームを行う際の注意点
その1:事前の確認と手続き
「共用部」に関わるor構造に影響がある工事は、管理組合への申請や承認が必須ですので注意しましょう。
その2:工事申請書の提出
多くの場合、工事の内容や期間、施工業者の情報を記載した「工事申請書」の提出を求められます。
工事時間や騒音、資材の搬入出などに関する細かなルールもあるため、着工前に必ず確認しておくことが大切です。
その3:業者選び
施工業者を選ぶ際は、団地や集合住宅の工事経験がある会社を選ぶと安心です。
専有部・共用部における工事可否の判断や工事申請などの段取りを熟知していますし、共用部の使用や他の住民への配慮にも慣れているため、工事をよりスムーズに進めてもらえます。
まとめ
団地でのリフォームは戸建て住宅と違って制約がある一方で、きちんと手続きを踏めば今までとは見違えるほど快適な住まいへと生まれ変わらせることができます。
リフォームの検討をはじめた段階からしっかりと管理規約を確認し、信頼できる業者と一緒に進めていきましょう。
団地のリフォーム・リノベーションについては、ホームプラスまでお気軽にご相談ください。